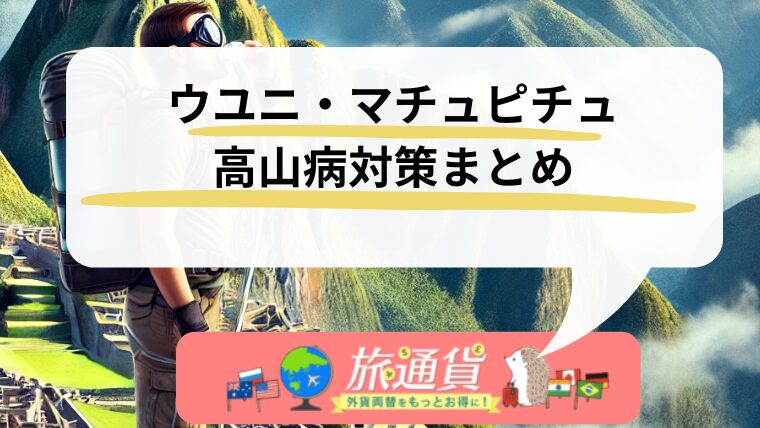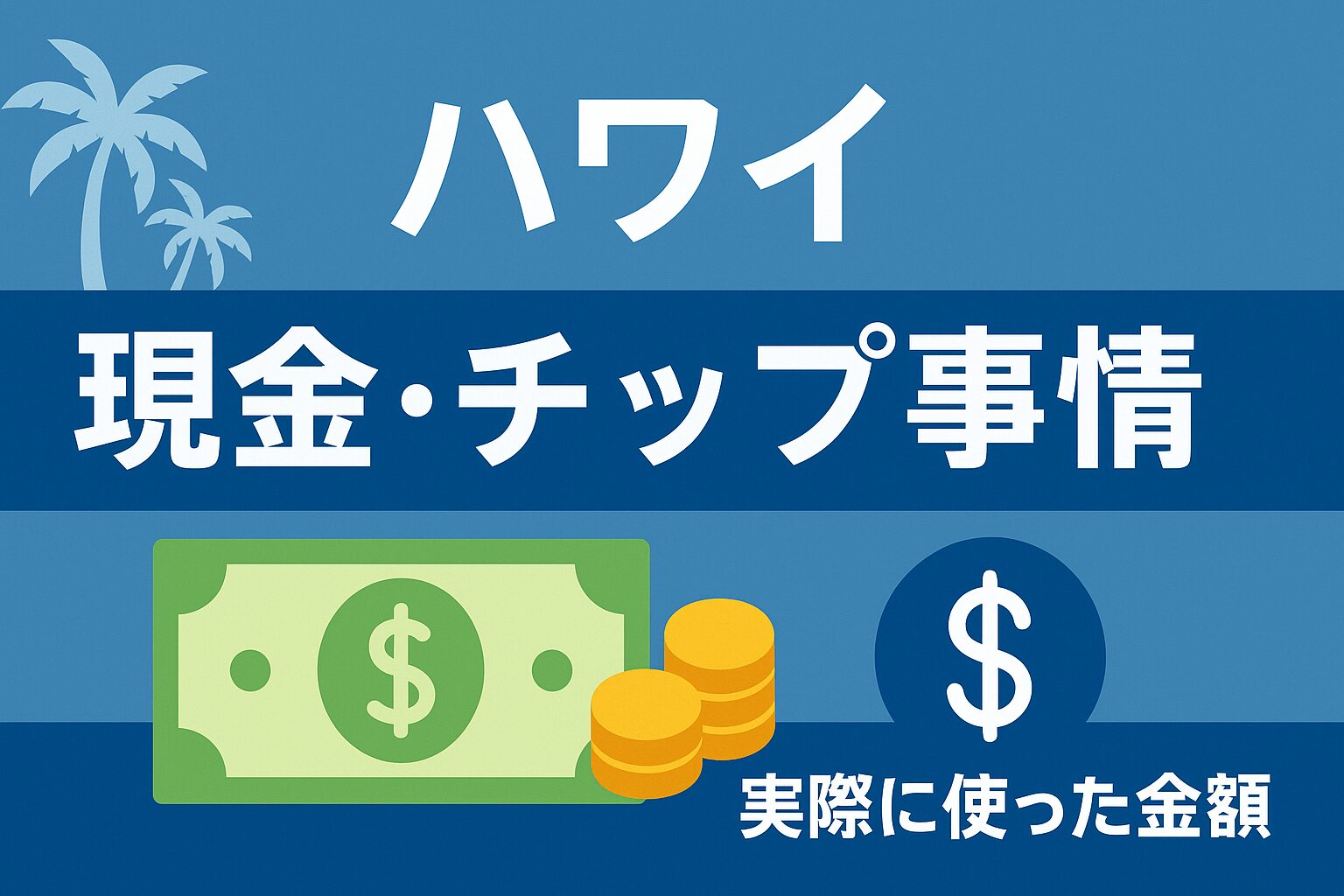2025年3月に南米のペルーとボリビアを巡る旅で、標高2,500~4,000mという高地を5~6日間かけて周遊しました。
訪れたのは、クスコ(約3,300m~4,000m)からマチュピチュ(標高2,500)、そしてラパス経由でウユニ塩湖(約3,600m)。
高地ならではの絶景に感動する一方で、予想以上に高山病の大変さを実感した旅でもありました。
本記事では高山病の基本情報から、高山病予防薬のダイアモックス服用体験、現地で感じた症状や対策などをまとめてご紹介します。これから同様のルートを旅する方は、ぜひ参考にしてみてください。
高山病とは?原因と症状
高山病(高度障害)は、標高2,500mを超える高地に急に移動した際、酸素濃度の低下に身体が対応しきれず引き起こされる症状です。
高山病の原因
- 急激な標高上昇による酸素不足
- 高地での体液バランス変化(脱水や血中酸素量の低下)
- 休息不足・寝不足・体調不良のまま登る
たとえば標高4,000メートルだと平地の約60%の酸素しかありません。
標高2,500メートルでも平地の約75%程度です。
低酸素によってさまざまな体調不良が起こるようです。
一般的な症状
- 頭痛、吐き気、めまい
- 息切れ、動悸、疲労感
- 食欲不振、睡眠障害
個人差はありますが、標高が高くなるほど症状が出やすいとされています。重症化すると、高地肺水腫や高地脳浮腫など危険な状態に陥る場合もあります。
高山病予防薬「ダイアモックス」について
高山病の予防・症状緩和によく使われる薬がダイアモックス(アセタゾラミド)です。日本国内では医師の処方箋が必要な薬なので、渡航前に病院で相談しておくと良いでしょう。
ダイアモックスの一般的な働き
- 血液中の炭酸水素イオンの排出を促進し、呼吸を早めることで酸素摂取量を増やす
- 身体が高地環境に慣れるのをサポートする
高地登山や高所でのトレッキングなどでもよく使われますが、薬には個人差がありますので、事前に医師と相談し、自分の体質や健康状態を踏まえて服用の可否や方法を確認することが大切です。
ダイアモックスの処方できる病院
私はKARADA内科クリニック渋谷店で2,970円、同伴者はオンライン診療のうかいクリニックで4,500円ほど(吐き気止め含む)で処方を受けました。
到着前日から朝晩半錠ずつ5日間飲むことで予防になるとのこと。
薬には利尿作用があるため、水をたくさん飲むことも大事で、一日2~3リットルを目安にしました。
簡単に処方してくれたわ!
実際に起きた高山病の症状
今回の旅では、クスコ到着前日からダイアモックスを服用していましたが、それでも初日はかなり息が上がる症状に悩まされました。
呼吸が乱れる・心拍数が上がる
- 階段で2階に上がるだけでも息切れ
- 短い登り坂を歩いただけでも心拍数急上昇
- 深呼吸しても息が戻りにくい感覚が続く
- AppleWatchが平均心拍数の大幅上昇を警告
普段の生活では感じない負荷を強く感じました。初日・2日目はとにかく無理をせず休むことを心がけるのが大事だと痛感しました。
高地に慣れてきた後半
日を追うごとに、身体が高地に慣れていったのか症状はかなり軽減。
最終的にウユニ(約3,600m)に到着した頃には、「空気が薄い」という感覚がほぼ気にならなくなりました。とはいえ、走ったり激しい動きをするとすぐ息が上がるので、行動にはまだ注意が必要でした。
心拍数の推移
クスコに移動した日から心拍数が目に見えて上昇してAppleWatchから心拍数の警告が出るレベルでした
安静時心拍の平均も上がってるけど 外で活動中は 普段100を超えることは稀なのに高地にいる間は110~130ぐらいをキープしていました。
高山病で酸素不足で息切れしていたのが 目に見えて数字にも出てました。
※青枠が高地にいた期間
初日がそこまでではないのは昼にリマ(標高100メートル以下)からクスコ(標高3500メートル)に移動した平均値のためやや低かっただけで クスコ単独だったらもっと高かった気がします。


ダイアモックスを飲んで感じたこと
今回の旅では、
- クスコに着く前日から服用
- 1日2回を継続
- 6日目の朝まで飲み続けた
おかげで重篤な症状(頭痛や吐き気など)はほとんどなく、行動は十分こなせました。 一方で、以下のような副作用も多少感じましたが、支障をきたすほどではありませんでした。
副作用
- トイレの頻度増加
- 手の指先の軽いしびれ
こういった症状はダイアモックスでは比較的よく知られているもので、特に強く気になることはありませんでした。
その他の高山病対策
ダイアモックス以外にも、現地では以下の対策を実行しました。特に、コカ茶やコカの葉はペルーやボリビアの高地で一般的に親しまれています。
コカ茶・コカの葉
- 現地ガイドからもらったコカの葉を長時間噛む
- コカ茶を頻繁に飲む(薄い抹茶のような味)
- 日本へ持ち帰りは禁止なので注意(法律違反になる)
コカの葉を噛んでも「トリップする」ようなことはなく、高山病対策の民間療法として定着している印象でした。
水分・アルコール管理
- 水分をこまめに摂る
- お酒は極力控える(酔いが回りやすい)
- 最終日夜にビール350mlを1本飲んだら、普段より酔いが早かった
高地では酸素が薄いだけでなく乾燥しがちなので、脱水状態になると高山病リスクが上がると言われています。こまめな水分補給は想像以上に大事でした。
無理をしない
高地ではとにかく心拍数が上がりやすいので、「少しでもつらい」と思ったらすぐ休むのが鉄則です。 後半になるほど身体が慣れてきて高山病の症状は落ち着きましたが、初期段階で無理をすると長引く可能性があるので要注意です。
旅程の流れと標高の変化
実際の旅程は以下のようなスケジュールで、3,300m以上の高地に連日滞在する形でした。
- 初日:クスコ(約3,300m~4,000m)
┗ モライ遺跡・マラス塩田など見学 → 夜にマチュピチュ方面へ移動 - 2日目:マチュピチュ見学 → 夜にクスコへ戻る
- 3日目:ラパス(約3,600m)へ移動
- 4日目:ウユニ(約3,600m)へ移動 → 塩のホテル宿泊
- 5日目:ウユニ観光
- 6日目:ラパスへ戻り旅終了
標高差が激しいエリアを短期間で移動するので、体調管理には十分注意が必要。日本への帰国後には、日本との寒暖差によって風邪をひいてしまいました。これも含めて、旅行中だけでなく帰国後も体調をよくチェックすることが大切です。
ちなみにラパス空港で人生初の4,000m越えを体験
3日目なのでだいぶ体が慣れてきてたけど 空港でスーツケース運んでるだけで息が上がってました。
まとめ:高山病対策は万全に
- 高山病を侮らず、必要に応じてダイアモックスなどの予防薬を利用する
- 体調が悪化したらすぐ休む。無理せずこまめに休憩をとる
- コカ茶やコカの葉、水分補給でサポート
- お酒は控えめに、酔いが回りやすい点に注意
- 後半になると慣れで症状は徐々に和らぐ
クスコやマチュピチュ、ウユニといった標高の高い地域は、他では味わえない素晴らしい絶景や文化体験が目白押しです。その分、身体への負担も大きいので、しっかり準備をしてから旅に挑んでくださいね。
また、最終的な薬の服用や体調管理に関しては、自己判断だけでなく医療機関での診察を受けることをおすすめします。安全で楽しい旅をお過ごしください!
以上、「高山病対策」についての体験レポートでした。
旅がより快適になりますように!
※本記事は個人の体験や一般的な情報を元にまとめたものであり、医学的アドバイスを保証するものではありません。服用・治療などは必ず医師にご相談ください。